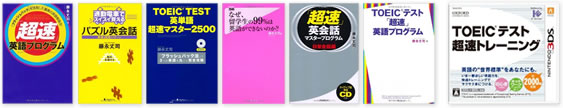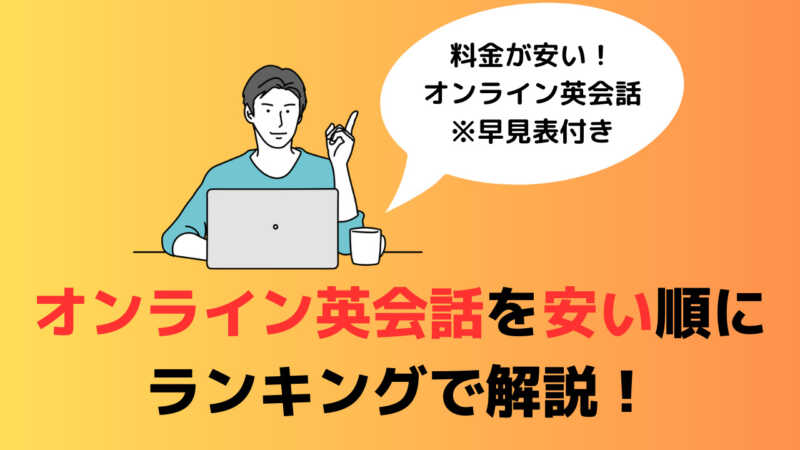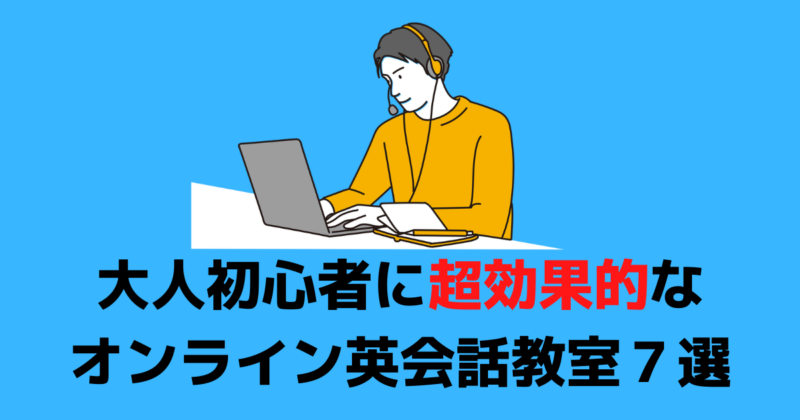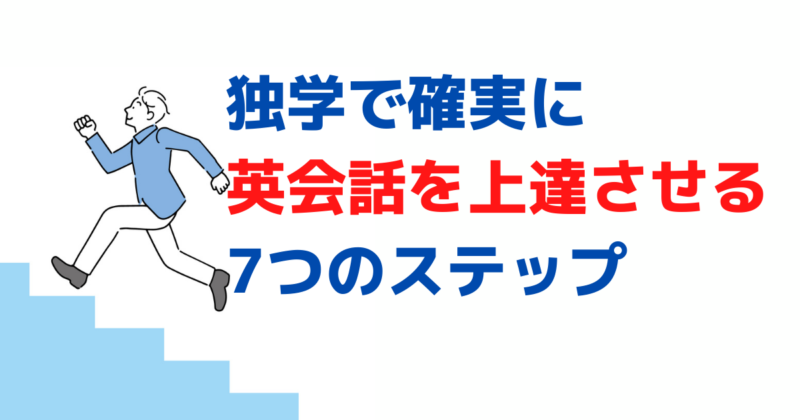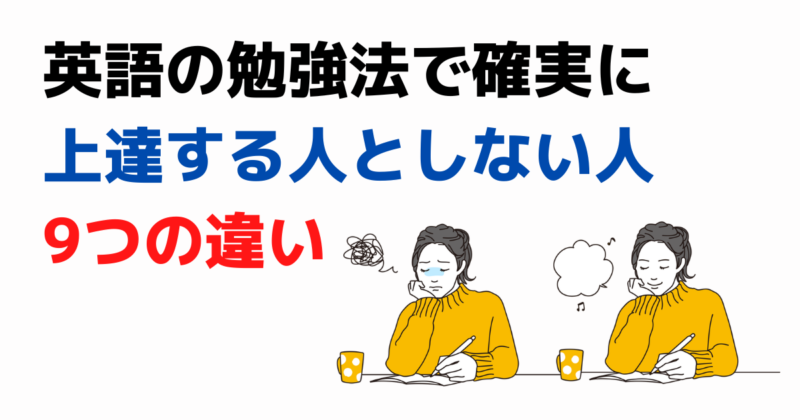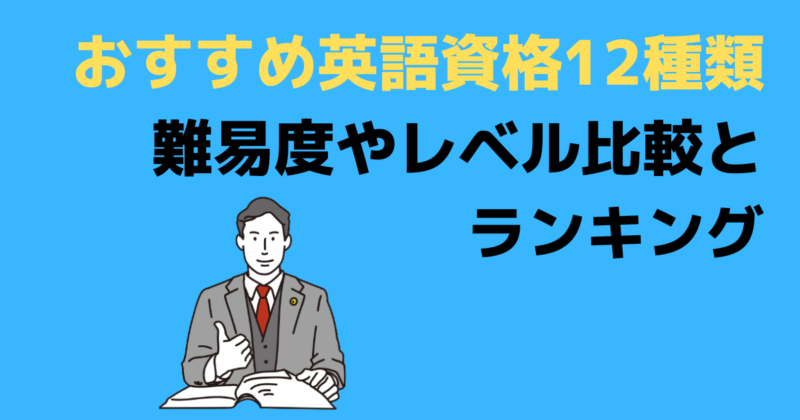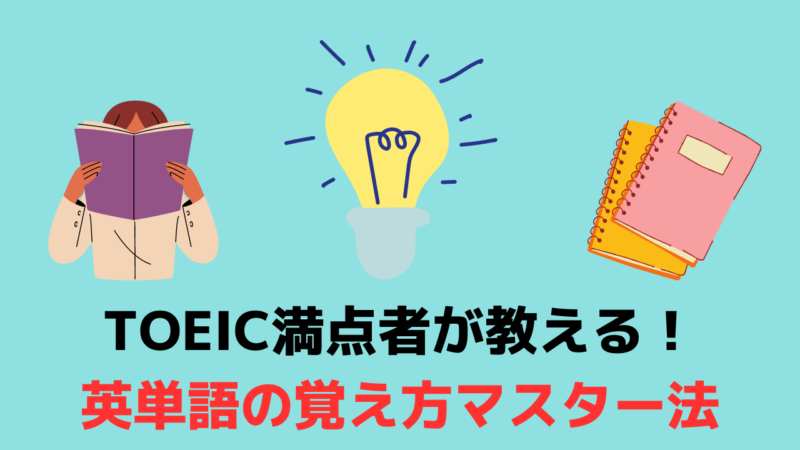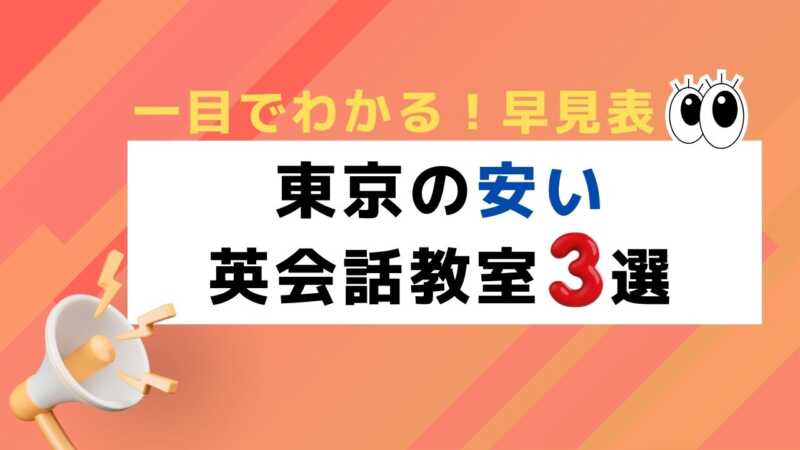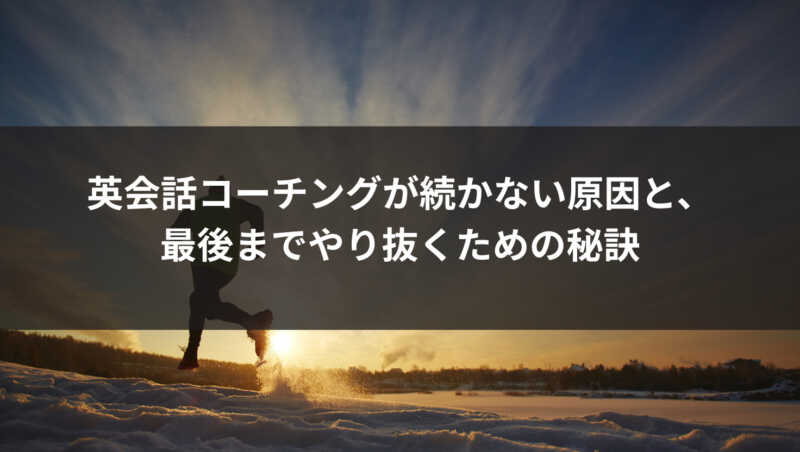
「英会話コーチングを始めたけど、途中でやめてしまった…」
「最初はやる気があったのに、3週間後には教材がホコリをかぶっていた」
英会話コーチングは短期間で成果を出せるサービスですが、続けられる人と途中で挫折する人がはっきり分かれます。
この記事では、心理学・行動科学の視点も交えながら「なぜ続かないのか」を解明し、最後までやり抜くための実践的な方法をお伝えします。
目次
英会話コーチングが続かない3つの心理的要因
1. 成果が見える前にモチベーションが切れる
多くの人は「効果が見えない期間」にやめてしまいます。
これは「モチベーションの崖」と呼ばれる現象で、心理学的にも説明が可能です。
人は努力の成果が実感できるまでに一定の時間がかかりますが、この期間を乗り越えられないと「自分には向いていない」と思い込んでしまうのです。
英会話の場合、リスニング力→スピーキング力の順で成長するため、「話せる実感」が出るのは早くても2〜3ヶ月後。
このタイムラグを知らないと、早々に諦めてしまいます。
2. 完璧主義による“発言のブレーキ”
「文法間違えたらどうしよう」「発音が変だったら笑われるかも」
こうした完璧主義は、アウトプットの機会を奪い、結果的に成長スピードを落とします。
実は、コーチング受講者で半年後も残っている人ほど、序盤から間違いを恐れず発言しているというデータもあります。
上達のカギは「正確さより発言量」。完璧は後から整えればOKです。
3. 習慣化の設計ミス
続かない人は、最初から「気合い」で乗り切ろうとする傾向があります。
しかし、行動科学では「意志力」よりも「仕組み」の方が継続力に直結するとされています。
例:
・毎日同じ時間・場所で学習する
・コーチに毎日報告する(義務感を活用)
・“やらないと気持ち悪い”状態をつくる
これらがある人ほど、英会話コーチングを最後まで走り抜けます。
行動科学でわかる「続かない人の学習パターン」
行動科学では、人が新しい習慣を定着させるまでのプロセスは3段階に分かれます。
- 開始期(1〜3週間):新鮮さとやる気で動けるが、効果はまだ出ない
- 停滞期(4〜8週間):慣れて飽きが来る。効果が見えずモチベ低下
- 定着期(9週間〜):習慣が自然に回り出し、効果を感じやすくなる
多くの人は停滞期で挫折します。
逆に言えば、この時期を越える仕組みを持てば、最後まで続けやすくなるのです。
続けられる人がやっている5つの工夫
1. 「目的」と「期限」をセットで決める
「半年後の海外出張でプレゼンする」など、期限付きの目標は学習の推進力になります。
期限があることで、毎日の行動に“意味”と“緊急性”が生まれます。
2. 小さな達成感を毎週つくる
脳は報酬で動きます。
「今週は電話会議で1回発言できた」など、小さな成功を積み重ねると、モチベーションが自動的に上がります。
3. コーチに弱点をさらけ出す
「聞き取れない音」「言えない表現」を隠してしまうと、改善が遅れます。上達する人ほど、弱点をそのまま見せ、コーチと二人三脚で修正しています。
4. 学習環境を“物理的に”固定する
机の上に教材とノートを置きっぱなしにする、オンラインレッスン用のスペースを作るなど、行動までのハードルを下げます。
5. 録音・記録で進歩を見える化する
週ごとに自分の発音や会話を録音し、過去と比較しましょう。成長が数字や音声で見えると「やってきてよかった」という感情が強まります。
コーチング効果を最大化するための“心の持ち方”
英会話コーチングは、「短距離走」ではなく「短期集中マラソン」です。
最初から全力疾走すると息切れします。
大切なのは、適切なペース配分で最後まで走り抜けること。
また、「今日はやる気がない」と感じる日があってもOKです。習慣化の研究によると、全体の80%の日数で継続できれば成功とされます。
完璧を求めず、淡々と続ける力が成功の分かれ目です。
まとめ:続かない原因を“設計”で解決する
英会話コーチングが続かないのは、才能や性格の問題ではありません。
多くの場合は、学習の設計や環境に原因があります。
・効果が出るタイムラグを理解する
・習慣化の仕組みを作る
・停滞期を越える工夫を持つ
これらを意識すれば、最後までやり切れる可能性は格段に上がります。
本気で英語力を伸ばしたい方は、まず自分が続けられる仕組みを一緒に作ってくれるコーチを探してみましょう。
行動を変えたその日から、英語力の成長曲線は上向き始めます。