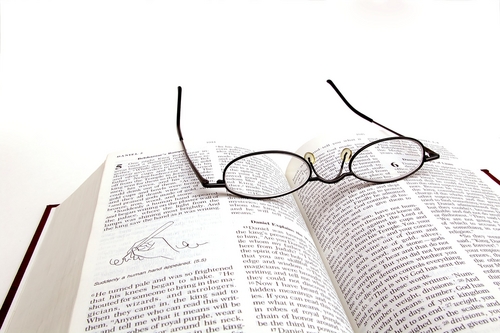
英語の論文が読めるサイトや書き方を知りたいですか?
医学などの専門分野で発表される方だけに限らず、何かの情報を知りたい時にも海外の論文を見ることもあるかと思います。
英語の論文は日本語の文章作成と違う点がいくつもあり、ある程度の書式やマナーが決まっています。
そのため、論文を作成する前にそのルールを知っておく必要があります。
それと、人工知能(AI)チャットのChat GPTやGeminiを使った英語の論文の添削方法や書き方のアドバイスの確認方法も紹介していますので、参考にしてみて下さい。
目次
英語の「論文」について
一般的に、「論文」は英語で「essay」や「paper」などと言われます。
その違いを下記で確認してみましょう。
- 「essay」:大学の授業などでも頻繁に書くようなどちらかと言うと小論文に近いイメージです。
- 「paper」:「essay」と同じような使い方をしますが、学会などで発表する論文は「paper」とい表現するのが一般的です。
- 「monograph」:専門的な論文
- 「thesis」:学位を取るための論文
英語の「論文」が読めるサイト
英語の論文を読むために利用できるいくつかのオンラインサイトがあります。
- PubMed Central (PMC):
- PubMed Centralは、医学分野の論文を中心に広範な分野の論文が無料で閲覧できるリポジトリです。
- IEEE Xplore Digital Library:
- IEEE Xploreは、工学、電気工学、情報技術に関する論文が掲載されているデジタルライブラリです。
- JSTOR:
- JSTORは、人文科学、社会科学、自然科学など幅広い分野の論文や学術書が収められているデジタルアーカイブです。一部は無料でアクセスできますが、全文へのアクセスには登録や購読が必要な場合もあります。
- ScienceDirect:
- ScienceDirectは、科学、技術、医学分野の論文を提供しているデータベースです。一部は無料で閲覧できますが、全文にアクセスするには購読が必要な場合があります。
- arXiv:
- arXivは、物理学、数学、コンピュータサイエンスなど多岐にわたる分野のプレプリント(査読前の論文)が公開されているサイトです。
- Google Scholar:
- Google Scholarは、学術論文、学会発表、書籍、論文引用などを検索できるGoogleのサービスです。多くの場合、リンクをたどって論文にアクセスできます。
これらのサイトは、異なる分野の研究に関する論文を提供しています。興味のある分野に合わせて適切なサイトを選んでください。なお、一部の論文は有料でアクセスできるものもあるため、検索結果から無料で利用できるものを選ぶことが大切です。
日本の学術情報や論文が読めるサイト
CiNii、J-STAGE、および学術機関リポジトリ(IRDB)は、日本の学術情報や論文を検索・閲覧できるサイトになります。
- CiNii (Scholarly and Academic Information Navigator):
- CiNiiは、日本の学術論文や図書などの情報を検索するためのポータルサイトです。CiNiiは国立情報学研究所(NII)が提供しており、多くの大学や研究機関の論文データベースをまとめて検索できます。
- J-STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic):
- J-STAGEは、日本の学術誌や学会論文などを提供する電子ジャーナルプラットフォームです。多くの学会が参加しており、幅広い分野の論文が閲覧できます。
- 学術機関リポジトリ(IRDB):
- 学術機関リポジトリは、各大学や研究機関が自らの研究成果を公開するデジタルリポジトリです。これには博士論文や研究論文、学会発表論文などが含まれます。リポジトリにはアクセス制限がある場合もありますが、多くの場合はオープンアクセスで一般の人でも利用できるようになっています。
これらのサービスは、日本の研究者や学生にとって非常に重要で、特に日本語での学術情報を探す際に有用です。それぞれのサイトを利用して、特定の分野や面白いテーマに関する論文を探せたり、必要な情報を入手することができます。
英語の「論文」作成の準備
ここからは、英語の論文の書き方について紹介します。
まずは、英語の論文を書く前段階として、書きたい内容をと目的を明確にします。
目的についてですが、大学の課題として書く場合と、研究者として学会で発表したり、ジャーナルに掲載されたりすることを目的とする場合では書き方が変わってくるでしょう。
論文作成前には、書きたい内容に近い分野の過去の論文や書籍をたくさん読む必要があります。過去の研究に同じ物が無いかや、似た内容の研究から自分の研究のヒントを得るためです。
また、内容だけでなく過去の英語の論文を読むことで、これから書く論文の様式、書き方の参考にすることができます。たくさん読む中で、読みやすいと感じる論文がいくつかあると思います。
その論文の様式、書き方を参考にすると論文が書きやすいです。
「論文に最適な文字のフォントや大きさとかは?」
英語の論文を書く場合、フォントは「Times New Roman」で、文字の大きさは「12ポイント」で書くのが一般的です。
また、1文あたりの長さは20語くらいが目安と言われています。論文で書く文は長くなりがちですが、適度に文を区切ることで伝えたいことが明確に伝わりやすくなります。
英語の「論文」の構成
一般的な論文の構成はだいたい決まっています。
正式な論文の場合は以下のような構成で書かれることが一般的です。専門分野や、作成目的によって構成内容が若干変わる場合があります。
事前に、過去の論文を確認したり、専門分野について詳しい人に相談したりして十分確認しておくことをオススメします。
- Title:タイトル
- Abstract:要旨
- Introduction:序論
- Methods:メソッド
- Results:結果
- Discussion:考察
- Conclusions:結論
- Reference:参考文献
- Appendices:付録
小論文の場合は「Abstract(要旨)」や「Literature Review(文献レビュー)」を等の部分を省略して、コンパクトにして書きます。
それぞれの構成部分の詳しい書き方、内容を確認しましょう。
論文構成|Title:タイトル
「Title」はとても重要です。
論文をウェブなどで検索する際に、最初に目にするのが「Title」です。この「Title」を見て、探している内容のことが書かれているかをまず判断することになります。必要な人に情報をとどけるためにも論文の内容がきちんとわかる「Title」を心がけましょう。
「Title」の語数は一般的に10~12語程度です。短すぎたり、長すぎたりすると、わかりにくくなるので気をつけましょう。
「Title」は「キャピタライゼーションルール」が適用されます。
「キャピタライゼーションルール」と例外
キャピタライゼーションルールとは「Title」の単語の頭文字を大文字にするルールです。
ただし、冠詞、不定詞の「to」、前置詞、等位接続詞は小文字にします。
※等位接続詞とは「and」、「or」、「not」、「but」、「for」などのことです。これらが小文字になります。
タイトルで気をつけたいポイントを確認しましょう。
- 簡潔であるか?
- 重要なキーワードが盛り込まれているか?
- 細かい文法的なミスはないか?
- 略語を使っていないか?
- 似た意味の単語、同じ単語を繰り返し使っていないか?
- 複数の意味を持つ単語のような曖昧な表現をしていないか?
- 疑問文にしていないか?(分野によっては疑問文も可能だが、一般的には避けたい)
論文構成|Abstract:要旨
「Abstract」は要旨で論文の要点をまとめた部分です。
大よその目安ですが200~300語で書くことが一般的です。論文の提出先によっては長さを指定されている場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
「Abstract」は短い文ですがとても重要な部分です。日々、たくさんの論文を読む忙しい人たちは、この部分をまず読んで論文の内容を大まかに把握します。この内容で、あまり重要ではないと判断されると残りの論文は読まれなくなってしまいます。
論文の中で重要なこと、一番伝えたいことをこの短い部分にしっかり盛り込みましょう。
この「Abstract」の部分は、実際はこの部分は最後にまとめます。論文が出来上がった段階で重要な点、伝えたいことを盛り込んで、論文の初めのところに配置する感じです。
「Abstract」に書く内容は本文中にある情報のみです。その中から目的、仮説と結論を簡潔に書きます。また、その結論に至るためにとった方法と、研究結果がどのような意味があるか、どのような影響を及ぼすかを述べます。
注意事項として、この「Abstract」の部分には略語、図表や引用文献などは記載しません。
論文構成|Introduction:序論
「Introduction」では研究の背景、目的、方法を伝えます。
この論文でどのような問題にチャレンジするのか、研究の内容、目的を明らかにします。
その上で、この研究以前に発表されている論文の研究成果などをまとめて、研究する必要があると考えるに至る背景を説明します。ここは、読み手に研究の重要性を伝える、とても重要なポイントです。
問題を解決するために、この研究で実際に使った検証方法を述べます。
最後に、その研究が社会に与える意義、メリットをまとめます。
ページ数はこの「Introduction」の部分を1ページ目とします。
ここで書いた内容が、本文の骨組みになるので「Introduction」はとても重要な部分です。
論文構成|Methods:メソッド
「Methods」では、問題を検証するためにどのような方法を使ったかを詳細に記載します。
論文構成|Results :結果
「Results」では検証方法から得られた結果と、そのことから発見したことを明確にします。
ここでは、図、表、写真など明確にデータや結果がわかるような資料を用いて説明します。図表を使う場合は、通し番号と「caption(簡単な説明)」をつけます。
結果については、既に研究が終了している時点で書くため、過去形を使って書きます。
論文構成|Discussion:考察
「Discussion」では研究の結果をもとに、その結果の意義や、新しい課題などを議論します。
問題に対して正しい結果が得られたかや、足りなかったと思われる部分、発見から考えられる新しい視点、課題など考察をまとめます。
論文構成|Conclusions:結論
「Conclusions」は結論をまとめる部分です。
結果から得られた重要な結論を記載します。
「Result」では得られた結果を詳細に記載しますが、ここでは一番重要なものだけピックアップして簡潔に述べます。また、「Result」で使った文をそのまま引用するのではなく、違ういい方に変えて書きます。
読者や社会に対して、研究結果から今後、何らかの行動を促したい場合はここに記載します。
この部分は簡潔に述べることが重要です。また、論文中で述べられていない新しい考え方はここには記載できません。
論文構成|Reference:参考文献
「Reference」には参考にした過去の論文、書籍や、文中に引用した文献を記載します。
この「Reference」は論文の本文ではありませんが、重要な部分です。論文を作成するにあたって、どのような過去の文献を確認したかは、論文の質にかかわる重要な問題です。
「Referenceは絶対に忘れない!」
文中で引用した文献についてはこの「Reference」で明確にする必要があります。正しく記載しないと、盗作(Plagiarism)となってしまいますの注意が必要です。
また、引用は「Paraphrasing」と「Quoting」の2つの方法があります。
- 「Paraphrasing」:同じ内容を自分の言葉に置き換えて書く方法
- 「Quoting」:著者の言葉そのままを引用する方法です。
もちろんどちらも、文中と「Reference」に記載が必要です。
論文構成|Appendices:付録
本文には載せられなかった詳しいデータなどは「Appendices」に入れます。
その場合、本文中の関連の箇所に「See Appendix A」など「Appendix」の記号、番号を記載しておきます。その上で、「Appendix」には対応する記号を記載します。
英語の「論文」で良く使う表現
論文でよく使う表現があります。ここでは、特に分野を問わず様々な論文で使えるフレーズをご紹介します。
英語論文で使えるフレーズ|【目的】
- The purpose of this study is …/この研究の目的は~だ。
- This paper examines …/この論文は~について調査する。
- The main objective of this paper is …/この論文の主な目的は~だ。
英語論文で使えるフレーズ|【内容】
- This study provides …/この研究は~を提供する。
- This paper reviews …/この論文は~について調査する。
- It has been often discussed that …/~についてはしばしば議論されてきた。
- In comparison with …/~と比較して
- In contrast to …/~と対照的に
- A agree with B./AはBと意見が一致している。
- A disagree with B in …/AはBで~において意見が違う。
- A can be defined as B./AはBと定義される。
- It is important that …/~は重要である。
- In order to …/~するためには
- It should be noted that …/~は強調されるべきである。
- The question remains that …/~についての疑問が残る。
- There is a possibility that …/~の可能性がある。
- This result suggest that …/この結果は~ということを提案している。
- We suggest …/~を提案する。
- On the one hand, …/一方では~だ。
- On the other hand, …/もう一方(他方)では~だ。
- As a result, …/結果として~だ。
- In general, …/一般的には~だ。
- In particular, …/ 特に~だ。
- In addition to …/~に加えて。
英語論文で使えるフレーズ|【図表】
- Table A shows …/表Aは~を示している。
- The graph A indicate …/図表Aは~と示している。
英語論文で使えるフレーズ|【引用】
- (人物)states that …/(人物)が~と言っている。
- (人物)claims ~/(人物)が~と主張している。
- According to(人物), …/(人物)によると~だ。
- (人物)mentions that …/(人物)は~と言及している。
- (人物)point out that …/(人物)はと指摘している。
英語論文で使えるフレーズ|【例】
- For example, …/例えば~
- For instance, …/例えば~
- One example of … is …/~のひとつの例として~がある。
英語の「論文」で使われる英単語
論文では、普段の会話などで使われない少し堅い単語を使う傾向があります。
- therefore:それゆえに
- thus:それゆえに
- hence:それゆえに
- however:しかしながら(一般的にbutを使う場面で使います)
- moreover:そのうえ(一般的にandを使う場面で使います)
- alternatively:そのかわり
- despite this:それにもかかわらず
- nevertheless:それにもかかわらず
- primarily:第一に
英語論文を翻訳して読みたい場合
英語が苦手のため、英語の論文を翻訳して読みたい場合、以下の翻訳アプリがおすすめです。
翻訳アプリ|DeepL
「DeepL翻訳」は、シンプルで使い勝手のよい人気の翻訳アプリです。DeepLの翻訳文は機械翻訳の中でも高い精度と自然な文の生成で評価されています。
音声翻訳とテキスト翻訳に加え、画像翻訳の機能も付いているので、幅広いシーンで活用できます。なお、無料版では、1回に翻訳できる文字数は5000文字までです。DeepL Proでは、どのプランでも文字数制限はありません。
PDFのレイアウトを保ったまま日本語翻訳|Readable
また、英語の論文のPDFなどを日本語に翻訳するとPDFのレイアウトが崩れる場合があります。これを解消したい場合には、「Readable」がおすすめです。
Readableなら、英語のPDFファイルをレイアウトを保ったまま、日本語に翻訳してくれます。
英語の論文を理解し読めるようになるには、以下のステップを試してみると良いでしょう。
- 基本的な英語力の向上:
- 論文は専門用語や複雑な表現が使われることがあります。まずは基本的な英語力を向上させるために、英単語の学習や文法の復習を行いましょう。
- 専門用語の理解:
- 各分野には専門用語が存在します。自分が興味を持っている分野の基本的な用語を理解することで、論文の理解が容易になります。
- アブストラクトの重要性:
- 論文を読む前には必ずアブストラクト(概要)を読みましょう。アブストラクトには論文の主要なポイントがまとめられており、これを読むことで全体の流れや結論が把握しやすくなります。
- 図表やキーワードの確認:
- 論文には時折難解な文章が含まれますが、図表やキーワードが理解を助けることがあります。これらを活用して論文の内容を理解しましょう。
- 文脈を理解する:
- 論文の文脈を理解することが重要です。論文が何を研究しているのか、なぜそれが重要なのかを把握すると、各セクションの内容もつながりやすくなります。
- 他の資料と照らし合わせる:
- 論文を読みながら、関連する参考文献や他の資料を参照してみましょう。これにより、新しい概念や手法に触れることができ、理解が深まります。
- 毎日少しずつ読む習慣をつける:
- 論文はしばしば密度が高く、一度にたくさん読むことが難しいことがあります。毎日少しずつ読む習慣をつけると、徐々に慣れていきます。
- 論文の構造を理解する:
- 論文は一般的にイントロダクション、メソッド、結果、ディスカッションなどのセクションに分かれています。各セクションの目的や構造を理解することで、論文全体の流れをつかみやすくなります。
これらのステップを組み合わせて、少しずつ英語の論文に慣れていくと良いでしょう。
Chat GPTやGeminiなどのAI(人工知能)チャットサービスを英語の論文の添削やアドバイスをもらうのに使うのもおすすめ!
英語の論文を完ぺきに書きたいなら、人工知能(AI)のチャットサービスもおすすめです。
例えば、次のようなプロンプト(命令文)を入力するだけで、添削や修正、またアドバイスをもらえます。
- 「自分で英語の論文を書いたのですが、添削をして下さい。修正箇所が分かるようにと、その理由も。」※この場合は、あなたが書いた論文をコピペして実行しますが、機密事項などある場合は注意して下さい。
- 「今度、英語で工業製品の論文を書きたいのですが、構成や例文などアドバイスを下さい。」
など。
まさしく、会話をしながらお願いする感覚でOKです。
この人工知能(AI)のチャットサービスにより、このような添削などが容易に可能になっています。この機会に試して下さい。
また、AIチャットサービスで有名なのが2つあります。
一つは「Chat GPT」です。OpenAIが2022年11月に公開した人工知能チャットボットであり、生成AIの一種で、無料版と有料版がありますが、正確な確認や訂正が必要な場合は、有料版をおすすめしています。

また、もう一つはGoogleが提供する「Gemini」です。

Chat GPT、Geminiのどちらも素晴らしい機能を提供しており、自分に合ったチャットサービスをご活用下さい。アプリもあるので気軽にスマホやタブレットでも使えます。
まとめ:英語の「論文」は基本が大事!
論文の書き方、構成についてご紹介しました。
ここでご紹介した構成は、全般的に使うことができる基本です。折角内容がよくても、基本の構成ができていなければ多くの人に読んでもらうことができません。
また、本文では触れませんでしたが正しい単語、文法を使うこともとても論文のできを左右する重要なポイントです。
文法については、ネイティブでもミスがあるくらいなので、できる限り英語に詳しい人にチェックしてもらいましょう。できれば、1人ではなく2人くらいにチェックしてもらうと、確認もれがなく正確な文章で仕上げることができます。
英語の論文が書けると、あなたの研究が世界の人に読んでもらえるようになります。初めは難しいと感じるかもしれませんが、パターンがあり、論文では頻繁に使える表現もたくさんあるので徐々に慣れると思います。
また、表現を増やしたい場合はネイティブが書いた論文をたくさん読んでみてください。その著者によりさまざまな、表現の傾向があり一つ読むたびに新しい表現を覚えることができます。

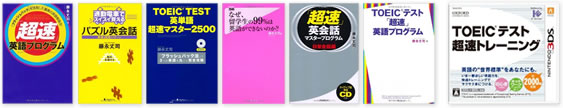



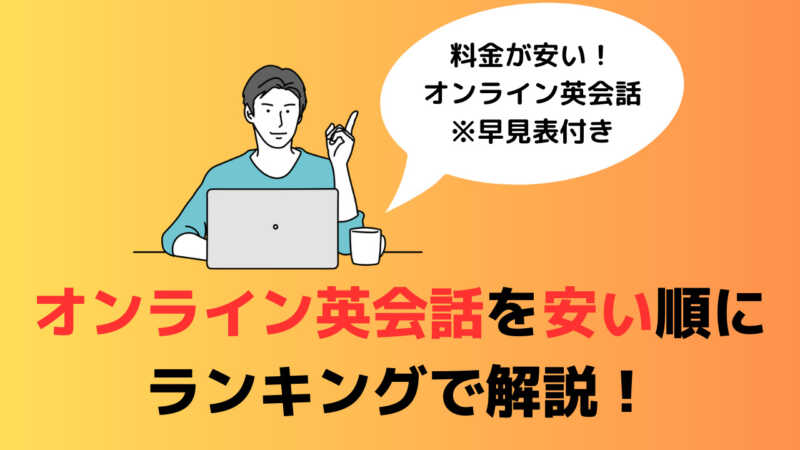

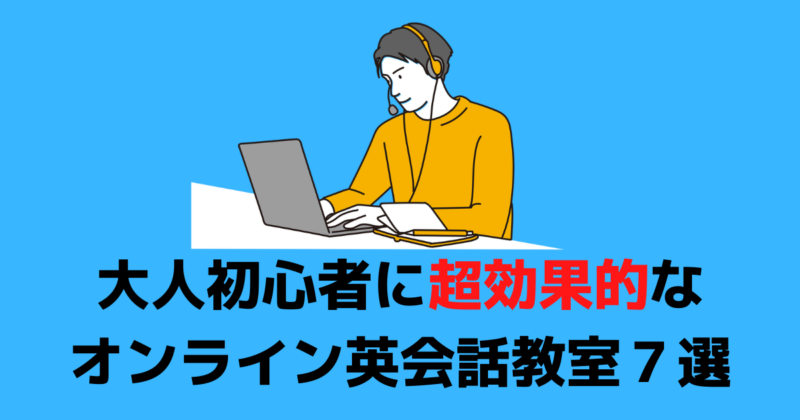
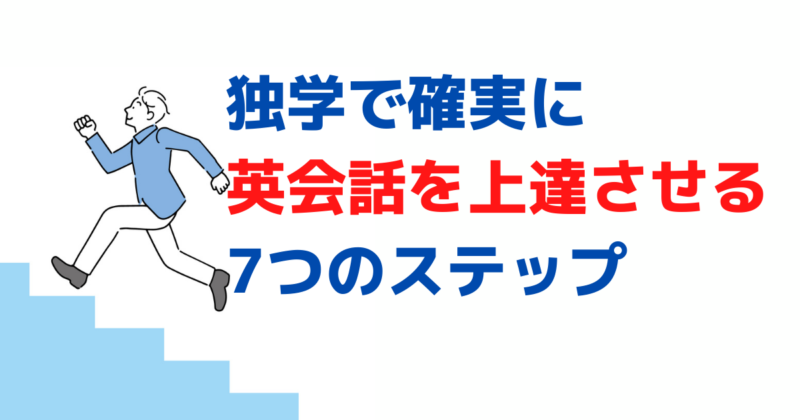
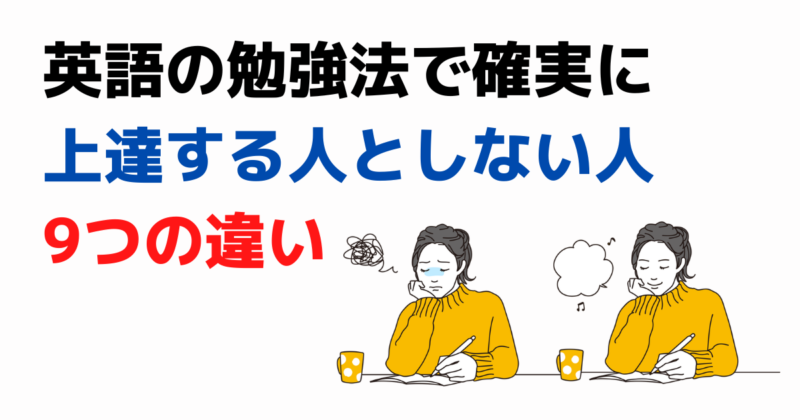
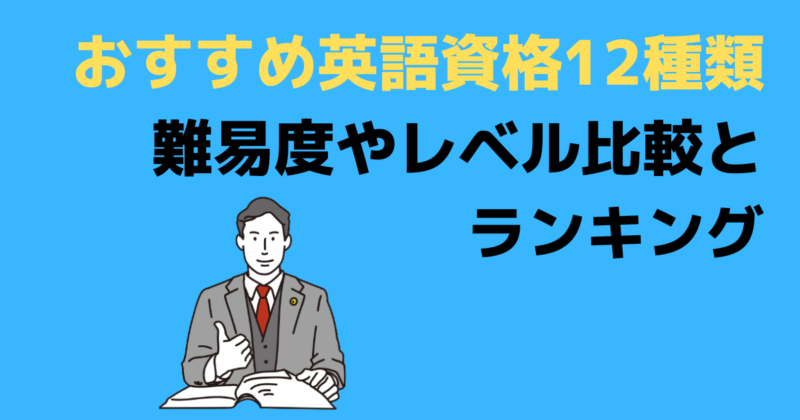
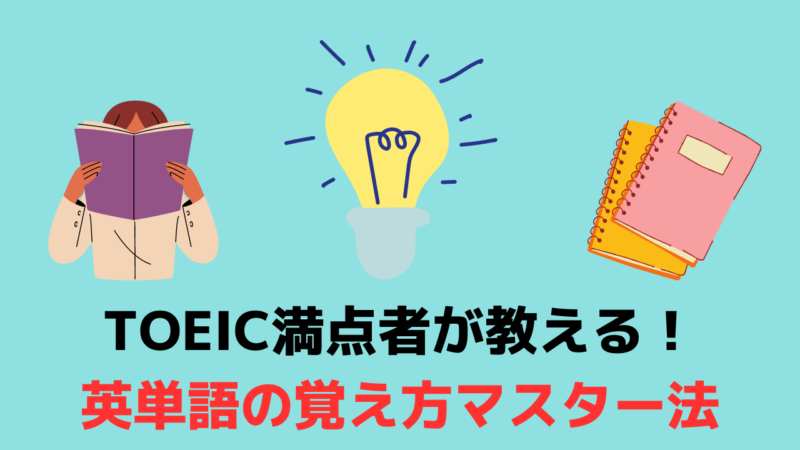
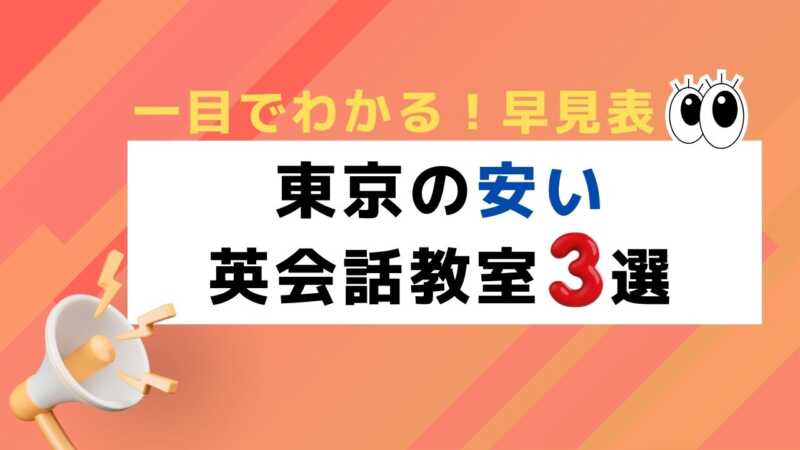



コメント